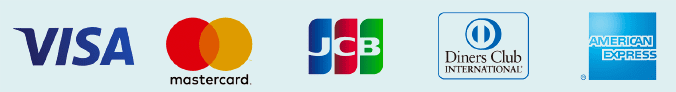シサムコーヒーのロングジャーニー
SISAM COFFEEの森から 第8話
「SISAM COFFEE」のコーヒー豆を届けてくれている
環境NGO「コーディリエラ・グリーン・ネットワーク(CGN)」の反町さんから
現地レポートの第8弾が届きました。
今回が今年最後のレポートです。
このコロナ禍で、コーヒーとそれに関わる多くの人たちがたどってきた、
長い旅路をぜひご一読ください。
////////

(ロックダウンが緩和され、急ピッチでシサムコーヒー輸出のための生豆の準備を始めました。)
シサム工房さんからようやく生豆が日本の倉庫に入ったという連絡が来て、
ほっとしているフィリピン・シサムコーヒーのふるさとからです。
シサムコーヒーの生産者の村の多くは、ベンゲット州という比較的私たちの拠点のバギオから近いところにあります。
ベンゲット州の農家の人たちは、稲作をやめ、お金になる高原野菜の栽培をメインとしている人がほとんどです。
つまり、主食のコメを買うために、何らかの野菜を売って現金収入を得なくてはならないわけです。
3月半ばからのフィリピン全土のロックダウンで一時的に野菜の卸売市場も閉まりましたが、
山の村の野菜栽培農家の命綱である野菜の販売は政府のサポートですぐ再開されました。
しかし、それでも、買い手がつかず、あるいは運搬手段が見つからず、野菜の価格は暴落しました。
育ててきた農家自身が野菜を廃棄せざるを得ない状況も起きました。
現金収入を絶たれた農家は苦境に立たされました。

3月半ばのロックダウン時、私たちはシサムコーヒー集荷の真っただ中でした。
私たちのシサムコーヒーの集荷のプロセスは、例年はこんな感じです。
1. 収穫期のはじまりに、フェアトレードのスタンダード(基準)に則り、パートナーの農家さんと農家さんの団体に前払い金をお支払いします。農家さんや農家組合はこのお金で人を雇って収穫や精製の作業をしたり、精製に必要な水や資材を買ったりすることができます。
2. 各農家で収穫、収穫後の精製、乾燥、選別などの作業を丁寧にしてもらいます。生産者農家の団体さんでコーヒーを生豆かパーチメント(内皮が残った豆)の状態で集めてもらい、連絡を受けたら私たちがそれを取りに行きます。
3. 私たちは、集めてもらったコーヒー豆をそれぞれ農家ごとに計量するとともに、水分率と選別の精度をチェックします。乾燥が足りなくて水分率が高いもの、欠点豆がちゃんと選別されていないものなどは、もういちど乾燥や選別をやり直してもらうこともあります。
4. それぞれのパートナー団体には「品質責任者」のような役割の人を決めてもらっていて、その人が責任をもって村のみんなが作ったコーヒー豆の品質をチェックしそろえる役割を担っています。

ロックダウンが始まった3月半ば時点で、シサムコーヒーの豆たちは以下のような状況にありました。
●すでに私たちの倉庫に入っているもの
●農家の団体で取りまとめられ、私たちのピックアップを待っているもの
●まだそれぞれの農家で精製や乾燥の作業中のもの
バギオと山の村との境が完全に封鎖された3月17日の前日、
3月16日にベンゲット州マンカヤン町のコーヒー農家さんが、小さな車にコーヒーを目いっぱい積んで6時間かけて私たちの事務所にやってきたのを最後に、コーヒー栽培地の農家との交流はプツンと途切れました。

外出移動規制の厳しいロックダウン中、倉庫管理スタッフが倉庫に住み込み、
湿度の管理と、まだ欠点豆が残っている生豆の選別、水分率の高い豆の乾燥作業をできる範囲で継続しました。
私たちのコーヒー豆担当のメインスタッフは隣町に住んでいて、9月に移動規制が緩和されるまでの半年間、
事務所にも倉庫にも来られませんでした。前払い金を受け取って納品ができていなかった農家の中には、
移動規制が少し緩和されたときに野菜運搬トラックのあきスペースにコーヒー豆を詰め込んで、
必死な思いでコーヒーを運んできた人もいました。
野菜販売による収入が減少する中、貯蔵のきくコーヒー豆の販売益は、農家の大きな助けになりました。
しかし、ロックダウン中に団体や個人農家で貯蔵していたコーヒー豆の中には品質の劣化が激しく、
残念ながら購入を断らざるを得ないものもありました。
この新型コロナウィルスの流行は世界中のすべての人に影響を与えました。
農家さんも苦境に立たされていますが、私たちも事務所と倉庫、それに併設していたカフェとゲストハウスを、
閉鎖せざるを得ない状況に追い込まれていました。

(シサムコーヒーへの輸出を終えたのち、カフェ、ゲストハウス、事務所、コーヒー倉庫のあった場所から転居しました。)
半年間の長い冬眠ののち、移動規制の緩和を受け、9月下旬からシサムコーヒーの日本への輸出に向けての作業を本格化させました。
倉庫の豆を、もう一度再チェックし、乾燥の具合から再度選別をし直す必要があると判断しました。
どうにも手が足りず、私たちのパートナー生産者のうち、バギオ市から一番近いトゥブライ町コロス集落のおばさんたちを毎朝&夕方、車で送り迎えし(公共交通機関がまったくなくなったままなのです)、朝から暗くなるまで選別作業をしてもらいました。
ロックダウンで移動ができず、野菜の行商にも行けず、人の畑の収穫手伝いのバイトもできず、道路工事の日雇いにも行けなくなっていた集落の人たちは、きっとバギオに来るのはちょっと怖かったでしょうけれども、ランチ付きの日当で喜んで一生懸命働いてくれました。


水分率がまだ高かった殻付きの豆(パーチメント)は、公共交通機関が少なくなって仕事が減ってしまった近所のドライバー男衆にお願いし、
面倒な移動許可証をとってもらって、お日様がさんさんと照っている山のふもとの村まで乾燥作業に何度も行ってもらいました。


私たちのNGOのスタッフは、選別や乾燥作業をしてくれるおじさんおばさんたちの炊き出し係でもあります。
買い物に行くのも行列の中、遠くから選別に来てくれるおばさん達にご飯とおやつを作り、毎日、彼女たちが帰った後に選別豆のチェックを行いました。

10トン近い生豆の選別と日本に向かうコーヒー豆5トンの梱包を終えたときには、ちょっとみんな泣きそうになりました。
このいまだ経験したことのない新型コロナ感染拡大によるロックダウンの中、マスクをしフェイスシールドを付け、ちょっと危険を冒しながらも、毎日、日本の皆さんにおいしいコーヒー豆を届けようとがんばった1か月の間にすっかり仲間意識が芽生えました。
そんな想いでようやくお届けできたシサムコーヒーです。
ぜひ寒い日の朝をほっこりシサムコーヒーで。

執筆: 反町眞理子
Mariko Sorimachi
1996年よりフィリピン在住。
2001年環境NGO「Cordillera Green Network(CGN)」をバギオ市にて設立。
コーディリエラ山岳地方の先住民族の暮らしを守り、山岳地方の自然資源を保全するために、
環境教育、植林、生計向上プログラムなど、数多くのプロジェクトを行っている。
2017年、CGNのスタッフたちとともに、社会的企業Kapi Tako Social Enterpriseを創立。
「SISAM COFFEEの森から 1~7」は >>こちらから<<
SISAM COFFEEの購入ページは >>こちらから<<