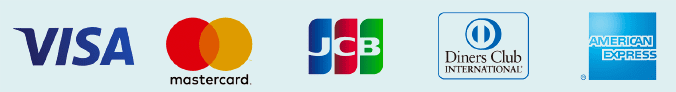Dear many hands 2≪後編≫
~拝啓、ネパールの母たちへ≪後編≫~
「私たちの日々の物語」を、作り手の皆さんに「お手紙」として届けるこの企画。
今回はネパールのフェアトレードNGO 「Sana Hastakala(サナハスタカラ)」です。
彼女たちが編みだす”特別なぬくもり”を知る、6人の女性たちのストーリー。
後半は、商品開発スタッフのワタナベを含む、3人のお話をお届けします。
長く大切に使えるものを

インタビュー当日、ハナタニさんが持ってきてくれた袋には、
手編みの品々がたくさん詰まっていました。
こうやって並べて見ると、「あぁやっぱり手編みって良いですね」と
二人でおもわずほっこり。

4~5年前に、初めてお店を訪れたハナタニさん。
言葉は知っていたけれど、具体的にはどういうことか知らなかった「フェアトレード」。
スタッフと色々と話していくうちに、すごく大切なことなんだなと感じるようになったそうです。
/////
“それからは、例えばスーパーでチョコレートを買うときなども、
フェアトレードのものを探したりと、少しずつ気にかけるようになりましたね。

/////
“昨年購入したカーディガンはソデが短いので、家で着ていても家事をしやすいのが嬉しいです。
寒い冬には本当にありがたい一枚。
さりげなく木のボタンを使っているところもお気に入りです。
温かさも特別に感じます。
他のニットを着た時とは、やっぱり違うんですよね。
なんだか中に温かな空気の層ができる感じ。
/////

/////
帽子もお気に入りで、昨年の冬も毎日のようにかぶっていました。
遊牧民族のパオがモチーフになった帽子だそうですね。
コーディネートの差し色にもなってくれます。
毎朝の自転車通勤には、耳付きの帽子に交代。
冬風から守ってくれるので、耳が痛くならなくてとても助かってるんですよ。

”今までは毎年の流行があって、いかに安く買って
次の年はこれが流行って、また買い替えて。
そんな繰り返しをしていたような気がします。
でも今は、流行りなんて関係なく長く大切に使えるものを。
シサム工房の服は、機能的なので、年中着られるものが多いのも嬉しいです。”
/////

―――生産者へ伝えたいこと―――
一つ一つ手づくりというのが本当にすごい。
きっと日々の生活の合間に、編み仕事をされているので大変だと思います。
服を一枚編み上げると思うだけで、気が遠くなるほど。
大事に着ないといけないなっていつも感じています。
それでいてデザインも本当に可愛くて。
いつも素敵なものを作ってくださり、ありがとうございます。
/////

ハナタニさんは、このインタビューをきっかけに、
少しでもフェアトレードを広げられたらと話してくれました。
/////
“これは押し付けるものではないし、興味を持ってもらえる人も一部かもしれない。
それでも、私みたいな話が、誰かのちょっとしたきっかけになれたら嬉しいです。”
/////
朝の通勤での一工夫。
寒い冬の家での過ごし方。
日々の暮らしのシーンに自然とフェアトレードが溶け込むハナタニさんの等身大の話こそ、
私たちの目指す「思いやりに満ちた社会」をつくる大切な種になる。
そう感じたインタビューでした。
つながっている

静岡県浜松市で、今年新しくフェアトレード雑貨店をオープンしたミムロさん。
実は15年程前まで、シサム工房のスタッフだった彼女は
そこで初めてフェアトレードというものに出会いました。
/////
“20年前の冬のある日、古材で作られた独特の雰囲気のお店に目がとまりました。
「外は寒かったでしょう。どうぞ中で温まってください」
そう書かれた貼り紙に何だか魅かれるものがあり、おもいきって扉をあけたのが始まり。
当時はまだスタッフも4人くらいで。
フェアトレードという言葉が全然社会に浸透していなかったところからのスタートでした。”
/////

15年以上前に購入したフェルトのポーチは今でもカメラケースとして愛用している品。
ネパールでは、「マチなし」のぺたんとしたポーチやかばんが多く、
マチ底が付いている商品の開発には苦労したそう。
当時の生産者のアイディアで、木箱を彫って、その型に沿ってフェルトを成型するという方法を
あみだしたそうです。
普段何気なく使っているものの細部には、おもわぬ知恵や物語が宿っているのかもしれません。
ミムロさんが今年オープンされたお店の名前は「晴天」。
まさに大空に浮かんだ雲を表現したこのポーチは、
出会うべくして出会った運命の品だとしみじみされていました。

/////
“手編みのキャップやレッグウォーマーもその頃から大切にしている品です。
子どもが大きくなったら使ってほしい思いがあり、今でもきれいな状態で保管をしています。
普段私たちは、目の前にあるモノを誰が作ったのか、モノの向こう側を考える機会は
あまり無いですよね。
その分、そんな情報をしっかり持っているフェアトレードの品は、
作り手をより身近に感じられるもの。
それだけで愛着が深まるし、大事に使おうと思うことができるんです。
―――生産者へ伝えたいこと―――
いつも温かみのある素敵な商品をありがとうございます。
誇りをもって、自信をもって、これからも頑張ってください。
そして笑顔で過ごせますように。
私も、そういう自分であり続けたいと思います。
生産者の皆さんのことをしっかり自分の言葉で伝えていきたい。
一つの商品を通じて、私たちはちゃんとつながっています。
いつか皆さんとお会いできればいいな。
/////

実はミムロさんのお店のオープン日は、シサム工房の創業日と同じ、4月25日。
/////
私なりの恩返しと敬意をもって、この日にしたかった。
一つのモノを通じて、生産者がどんな人か、どんな暮らしをしているのかを知ることができるのが
フェアトレードの良さ。
ぜひ気軽に手にとってほしいし、私のように愛着を持って大切に使えるモノたちに
たくさん出会ってほしい。
そのためにも、私ももっともっと勉強しないと。
/////
そう笑顔で話すミムロさんは、まさに「晴天」という言葉がよく似合う女性でした。
「作る人」と「使う人」。
目には見えないけれど、その間には確かにつながっている何かがあるのだと、
私は改めて彼女に教えてもらったように感じます。
私たちシサム工房もまだまだこれから。
場所は違えど、ミムロさんや多くの仲間とともに、目指す社会へ歩んでいきたいと思います。
たった一つのぬくもりを

シサム工房のなかで、サナハスタカラの生産者と一番身近な場所で、
長年共に仕事をしてきたのが、スタッフのワタナベです。
彼女たちと共に、数々の手編みやフェルトのアイテムを生み出してきました。
10年以上前に、お店にランプを買いにきたのが
シサム工房、そしてフェアトレードとの出会い。

前職でパソコンのグラフィック関係の仕事をしていたワタナベは、
均一なことが美しいとされる価値観のなかで日々を過ごしてきました。
そんななか次のステージへと転職を考えたとき、
「手仕事のものに関わる仕事をしたい」という想いがふつふつと沸いてきたといいます。

3年間の店舗スタッフ経験を経て、
6年前に、商品開発担当として初めてネパール出張をしたときが、
サナハスタカラの生産者との出会い。
/////
“作り手の人たちに実際に会えたとき、感動して胸が熱くなりました。
初めはとにかく緊張してましたね。
ネパールでは”YES”の時に、首を横にゆらゆら揺らすんですよ。
日本でその仕草は”NO”の意味に近いので、会話をしていて
「え!?だめなの!?」って最初は戸惑ったりもして。
でもそんな異文化に触れることも新鮮で楽しかったことを覚えています。
また生産者の人たちが真剣な表情で作業をしている様子をみて、
職人の緊張感ある空気や、技術に対する誇りも感じましたね。
私もしっかりがんばらないとと身が引き締まる思いでした。”
/////

作り手の技術に支えられながら商品を開発するなかで
ワタナベが直面したのは、手仕事のものを量産することの難しさでした。
/////
“「手仕事の良さ」と「商品として販売ができるもの」。
そこのバランスのコントロールが難しいんです。
初めはそのことにすごくストレスを感じていました。
ある手編みのマスコットを開発したときに、全然顔の違うものができてしまったんです。
均一なモノづくりに慣れてしまっていた私は、「なんで同じものが作れないの?」と
生産者にも強く注意して。
ただ、いざ販売してみると、お客様に「この顔一つ一つ違うのがいいね。」って
言ってくださる方が多かったんです。
ハッとしました。それは手仕事のあかしであり、良さでもあるんだって。”

“また、生産者さんの言葉で忘れられないものがあります。
『ハンディクラフトは魔法の言葉です。
これは手仕事だから、と安易に言うとすべて逃げることができてしまいます。
その言葉に逃げないようにクオリティを保つよう努力することが私たちの仕事です。』
手仕事だからといって、質の低いものは受け入れられません。
ものづくりへの真摯な姿勢とその難しさを実感した言葉でした。
フェアトレードのものづくり。作り手も買い手も嬉しいものづくり。
それはこちらの要望を一方的に押し付けるのではなく
生産者の技術や個性を活かしながら質を高めていくことが大切なんだと感じています。
正直難しいと思うことも多々ありますが、地道に現地に通っては、生産者の人たちに何度も伝えて。
それをコツコツと繰り返すことで、商品も年々良くなってきたことが嬉しいですね。”
/////

/////
”生産者の皆さんに「仕事をしていて楽しい時っていつ?」と尋ねたことがあって。
そしたら初めての商品を編み上げる時が一番楽しい!って答えてくれた人が何人かいました。
あぁ作ることが好きなんだなって。
日々の仕事のなかで、クリエイティブなこと、モノづくりそのものを楽しんでくれていること。
新しいデザインを楽しみにしてくれていること。
そのことに気づいて、一緒にモノづくりをしているんだ、繋がっているんだという実感をもてました。
ちなみにサナハスタカラでは夏用の帽子も毎年編んでもらっているんですが、
実はネパールには夏に帽子をかぶる習慣がないんです。
それでも日本で使う人のことを一生懸命想像しながら編んでくれているんだな。
そう思うと、本当に嬉しいですね。
/////

ワタナベの長年のお気に入りは、ルームシューズ。
/////
“私は寒いのが苦手なんですが、ルームシューズってめっちゃ温かいんです。
足に手編みのものを身に着けているという、なんとも言えない贅沢感と幸福感がたまりません。
使用してもう7年目ですが、だんだんと編み目が詰まってフェルトのようないい表情になり
ますます手放せない存在になっています。
全身が温まって、冬の日々を守ってくれているように感じます。
周りの人にも知ってもらいたくて、色んな人の贈り物にもしています。”
/////
―――お客様へ伝えたいこと―――
“同じ編み手さんでも、まったく同じものは仕上がらない。
手編みの商品は世界にただ一つ。 唯一無二なものだと感じています。
タグ一つにしても、実は全部手作業で付けているんですよ。
一本の糸から途方もない時間をかけてようやく編みあがる商品。
こうやって素敵な商品を販売できるのは、奇跡的なことだなと思うことがあります。
編み手が大事に作ってくれたものを
日本のお客さまが大事に使ってくれている。
たまに修理品ですごい昔の商品を預かったときに
「本当に大事にしてもらえているんだな」と思えて嬉しくなりますね。
きっとそれはその商品の向こうにいる人のことを感じとってくださっているから。
そんなつながりを感じられたとき、私は心から幸せな気持ちになります。
手編みのサイズ感や形が違っても、それが良い!と言ってくれて。
全く同じではないところに魅力を感じて、受け入れてくださる皆さまの寛大さが
多様性を受け入れる優しい社会にも繋がっていると思います。

―――生産者へ伝えたいこと―――
“いつも根気よく作ってくれて、ありがとう。
何から何まで手づくりで、本当に頭の下がる思いです。
納期を急かしてしまうこともあり、ごめんなさい。
サンプル一つ仕上げるのにも、手編みは時間がかかるのに
無理なリクエストにいつも全力で応えてくれてありがとう。
モノづくり自体を楽しんでやってくださっている人もいて。
毎年新しいデザインを楽しみにしてくれているのは
デザイナーとして何より嬉しいです。
楽しんで生産すること、それが何にも代えがたい温かみとなり
サナハスタカラの商品の魅力になっていると思います。
こうして一緒に長い間働けてることを、幸せに思っています。”
/////

冬の匂いをかすかに感じる11月。
真冬の寒さを思い出すと、体が縮こまってしまいますが、
私たちには、彼女たちが届けてくれた特別なぬくもりがあります。
そんなささやかな幸福を、少しでも多くの人に知ってもらえますように。
そんな願いを込めながら、6人のストーリーを
ネパールで暮らす作り手の皆さんへ、敬意と感謝を込めて贈ります。
FAIR TRADE LIFE STORE by sisam FAIR TRADE
タニ
//////
ネパールのフェアトレード団体「Sana Hastakala」のアイテムは >>コチラから<<
2019 Autumn&Winter collection は >>コチラから<<